
| この記事でわかること |
|
| この記事の対象者 |
|
| 効率化できる業務 |
|
「導入したのに効果が出ない…」その理由、見えてきました。
2025年6月、エクサウィザーズの調査結果が話題を呼んでいます。生成AIを導入した企業はどんどん増えているのに、実際に「費用対効果を感じている」と答えたのは、わずか18.9%。このギャップ、ちょっと気になりますよね。
実は、成功している企業には“共通の工夫”があります。単なるツール導入ではなく、「AIエージェント」として業務に深く組み込み、コア業務のパートナーとして活用しているんです。
この記事では、生成AIの現状と課題、成功企業が取り入れている実践的な活用法、そして導入時の落とし穴や対策まで、まるっとご紹介します。「ウチのAI、全然使われてない…」と感じている方、ぜひ最後まで読んでください!
生成AI導入は進んでいるのに「効果を実感」は2割未満?
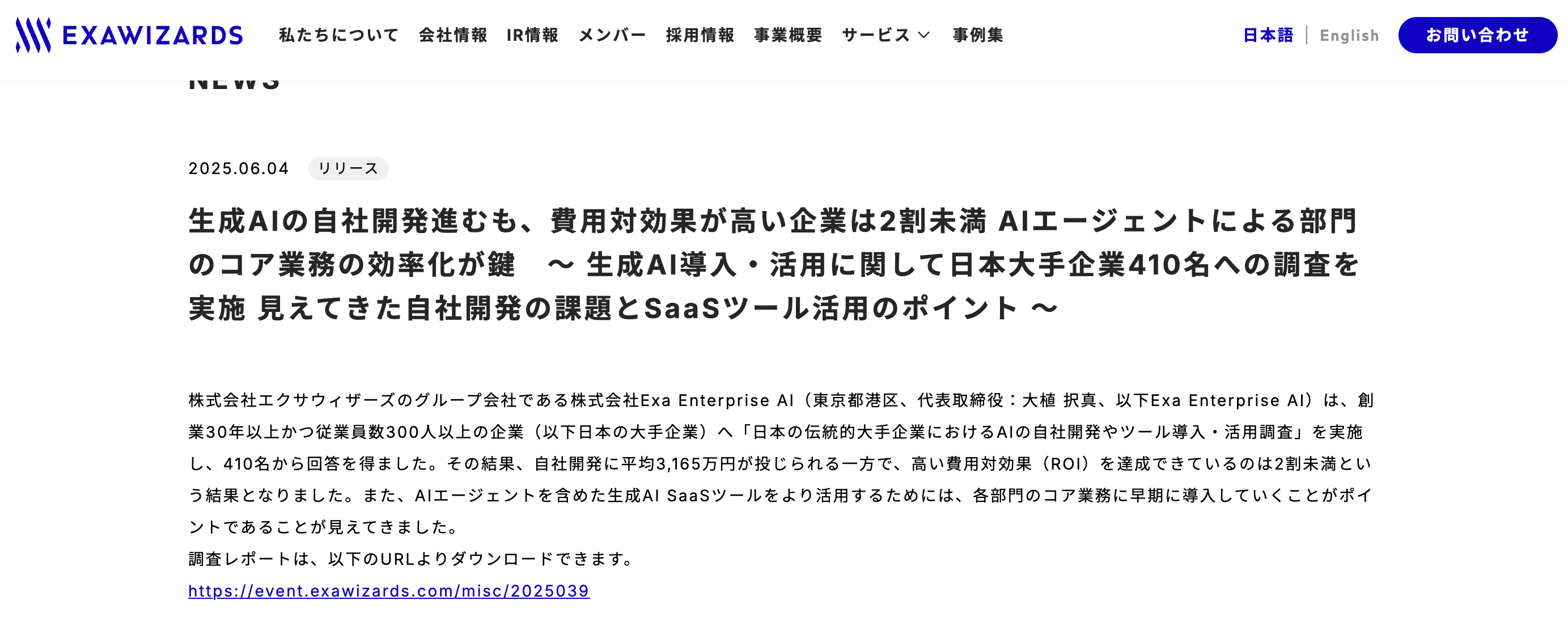
広がる導入と、実感できない成果の差に注目。
背景
2025年6月、エクサウィザーズが実施した企業調査によると、生成AIをすでに導入済み、もしくは導入を検討している企業は約7割にものぼります。ChatGPTやGeminiなどの登場で、「うちも何かやらなきゃ」と動き出した企業も多いのではないでしょうか。生成AIとは、テキストや画像、音声などを自動で生成するAI技術のこと。業務効率化やアイデア創出への期待が高まっています。
でも…注目度とは裏腹に、「導入してよかった!」と感じている企業はたったの18.9%。ちょっと意外ですよね。これは、導入しただけで止まっている企業が多いことを意味しています。
自社開発の比率とその実態
生成AIの取り組みの中でも注目されているのが「自社開発」。なんと、導入企業のうち38.5%が、自社向けにAIツールやエージェントを独自開発しているそうです。これは「汎用ツールでは限界がある」と感じた企業が、業務にピッタリ合ったツールを作ろうと動いている証拠ですね。
でも、自社開発=成功とは限りません。実際には開発に予算と人材を割いても、現場ではほとんど使われていない…なんてケースも多いんです。開発して終わり、ではなく、そこからが本番。いかに業務に根づかせるかが問われています。
表面的な活用と効果のギャップ
「とりあえず試してみた」だけで終わっていませんか?生成AIの導入には、つい「まずはやってみよう」という空気が漂いがち。でも、それだけでは成果は出ません。たとえば、資料の要約や議事録の自動作成など、スポット的な活用に留まってしまうと、費用対効果を感じにくくなります。
本来のゴールは、日常業務の中にAIを溶け込ませること。たとえば、営業メールの自動下書き、問い合わせ対応の自動化、レポート作成支援など、業務フローに組み込む工夫が必要です。使ってナンボ、回してナンボ。それができなければ、“宝の持ち腐れ”になっちゃいます。
成果を生まない理由とは?
「なぜ結果が出ないのか?」その答えは、導入後の設計と運用にあります。ありがちな課題を挙げると…
- どの業務に使うか明確に決めていない
- 現場の人が使い方を理解していない
- 継続的に改善していく体制が整っていない
つまり、AI導入が“プロジェクトで完結してしまう”んです。「導入して終わり」ではなく、「どう根付かせるか」「どう広げていくか」が本当の勝負どころ。それを見据えて準備しているかどうかで、成果に大きな差が出るんですよね。
成功企業が注目する「AIエージェント活用」の実態
成果を出している企業には共通点があるんです。
AIエージェントとは何か(定義と背景)
AIエージェントとは、人間の指示に従って特定のタスクをこなす自律型AIのこと。最近では、チャット形式で動く秘書型エージェントや、社内システムと連携して業務を処理する自動化エージェントなど、多彩な形で登場しています。
生成AIとの違いは、“その場の出力”にとどまらず、“継続的な行動”ができること。つまり、単なる便利ツールではなく、「業務を代替・支援する担当者」に近い存在なんです。AIに名前をつけて、まるで新入社員のように扱っている企業もあるほど。愛着すら感じますよね。
成果を上げている企業の活用パターン
「効果を出している企業って、どんなふうに使ってるの?」と思った方、気になりますよね。実際には、以下のような使い方が成果につながっています。
- コールセンターでのお問い合わせ対応の自動化
- 営業メールの下書き作成や提案書の草案作成
- 定型レポートの生成とデータの収集・整理
- 社内のFAQ回答やマニュアル提示の自動化
これらに共通しているのは、“繰り返し発生する業務をAIに任せている”点です。「ラクになった」「ミスが減った」と、現場からの評価も上々。要するに、人じゃなくてもできることはAIにお任せして、人間はもっと価値あることに集中できる環境をつくっているんですね。
コア業務の自動化と業務支援の違い
ここでちょっと注意したいのが、“支援”と“代替”の違いです。たとえば、AIに議事録の要約を任せるのは「支援」。でも、議事録の作成から共有、フォルダ整理まで任せると、それはもう“自動化”です。
成果を出している企業は、支援レベルに留まらず「完全自動化」に踏み込んでいます。しかも、単一業務だけでなく、前後のフローも含めて自動化することで、手離れのよさと再現性がグンとアップ。「これ、毎日人がやってたの?」と思うような作業をAIに渡して、働き方ごと変えているんですよ。
業務プロセス全体に組み込む視点
AIエージェントを“使い捨てツール”として扱ってしまうのはもったいない! 成功している企業ほど、AIを業務プロセス全体の中に埋め込む視点を持っています。
たとえば、営業プロセスなら、アポ取得→ヒアリング→提案書作成→日報登録…この流れのうち、2〜3工程をAIが担当。人は対話と意思決定に集中できるようになるわけです。
AIエージェントは「単なる機能」ではなく「業務パートナー」。その意識があるかどうかで、導入効果は天と地ほど変わります。そろそろ、AIと“チームを組む”感覚、持ってみませんか?
生成AIの効果を引き出す条件とは?
“導入するだけ”で満足していませんか?
効果を得ている企業に共通する条件
生成AIを活かしきっている企業には、いくつか共通点があります。「AIをうまく使ってるな〜」という会社って、たいてい次のような工夫をしているんです。
- 導入前に目的を明確にしている
- 担当部門と現場の橋渡し役が存在する
- 成果指標(KPI)を設定し、運用で改善している
- 「失敗してもOK」という文化が根づいている
つまり、“やって終わり”ではなく、“使いながら育てる”スタンスがカギ。最初から完璧を目指さず、試してみて、少しずつ調整していくことが成功の秘訣なんです。
業務フローの可視化とAIタスクの明確化
「どこにAIを入れるべきか?」が見えていないと、せっかくの技術も活かせません。成功している企業は、まず自社の業務フローを洗い出しています。「誰が、いつ、何を、どの順でやっているのか?」を図式化し、その中から“自動化できそうな部分”を発見していくんです。
このステップを飛ばしてしまうと、「とりあえず使ってみたけど、あんまり意味なかったな…」という残念な結果に。逆に、ここをしっかりやれば「この業務、まるっとAIに任せられるかも!」という発見にもつながります。
部門横断の連携とデータ整備の重要性
AI導入は、IT部門だけの仕事じゃありません!成功している企業では、営業、総務、法務など、さまざまな部門が連携してプロジェクトを動かしています。
「こんなデータがほしい」「こういう言い回しは避けて」など、現場の“生の声”が反映されるからこそ、AIも“現場仕様”に進化するんですね。加えて、データの整理やフォーマットの統一も不可欠。「データはあるけどバラバラで使えない…」という事態は、案外多いので注意です!
スモールスタートと継続改善のサイクル
いきなり全社導入!…なんて気合いは不要です。むしろ、うまくいっている企業ほど「まずは1部門」「1業務だけ」と小さく始めています。そして、現場のフィードバックをもとに改良を重ね、じわじわと広げていくスタイル。
この“スモールスタート→改善→拡大”のサイクルがあれば、リスクも最小限で済みますし、成功事例を社内で共有することで、ほかの部門も巻き込みやすくなります。最初の一歩を小さく、でも確実に。それが成功への近道です!
費用対効果を高めるには?AI導入の成否を分ける視点
お金の話、避けずにちゃんと考えましょう!
初期費用と運用コストの見積もり
AI導入って、なんだか高そう…そう感じる方も多いかもしれません。実際には、初期費用よりも「継続コスト」が意外と重くのしかかってくるんです。
たとえば、自社開発型のAIなら、要件定義・開発・テストだけで数百万円規模になるケースも。さらに、学習データの整備や保守対応など、開発後も費用は続きます。一方、クラウド型AIツールの場合は月額課金制が多く、長期で使うと累積コストが意外と高くなることも。
費用対効果を見積もるには、「何に」「どれくらい使って」「どれだけ業務を減らせるか」のシミュレーションが不可欠。ざっくりでも試算しておくと、導入の判断がグッとラクになりますよ。
無料ツール・既存SaaSの活用余地
全部ゼロから作る必要なんてありません!最近では、ChatGPTやNotion AI、Microsoft Copilotなど、すでにAI機能を備えたSaaS(サース:クラウド型の業務ソフト)もたくさん登場しています。
実際、「社内の資料作成はNotion AIで十分」「議事録は無料のWhisperで回してるよ」という企業も珍しくありません。こうしたツールを“活用前提”にしておけば、初期投資ゼロで成果を出すことも可能です。
無料だからといって侮れません。むしろ、「まずはここから試してみよう!」という入口としては最適。手軽に始めて、小さな成功体験を積み上げていくことが大切なんです。
内製か外注か、目的に応じた判断軸
自社で作るべきか、それとも専門業者に任せるべきか。この判断も導入前にしっかり整理したいポイントです。
内製のメリットは、自社の業務にフィットしたカスタマイズ性。でも、要件定義やAI人材の確保など、時間も労力もかかります。一方で外注は、短期間で仕上げられる反面、コストが高くついたり、柔軟な変更が難しかったりすることも。
判断の軸はシンプル。「このAI導入で得たい成果は何か?」「それはスピードが重視か?独自性が重視か?」この2つを軸に整理してみると、最適な手段が見えてきます。
PoC(概念実証)から本格展開へのプロセス
いきなり大規模導入に踏み切るのは、やっぱり怖いですよね。だからこそ、PoC(ピー・オー・シー:Proof of Concept=概念実証)で“小さく試す”ことが鉄則です。
PoCでは、対象業務を絞って仮導入し、「本当に使えるか」「現場の負担はどうか」「想定通りの効果が出るか」を確認します。ここでOKが出たら、次は本番導入。その後、対象業務を拡大していくのが王道パターンです。
この段階的なアプローチなら、現場の混乱も少なく、反発も最小限。社内理解も得やすくなりますし、費用のかけ方もコントロールしやすくなりますよ!
まとめ:生成AIは“使ってなんぼ”。本当の価値はこれから
生成AIは、導入することがゴールではありません。「何に使い、どう効果を出すか」が問われる時代になっています。自社開発や高機能なAIツールも、使われなければ意味がありませんよね。
成功している企業は、まずスモールスタートでPoC(概念実証)を行い、現場の業務に組み込む形で活用を広げています。そして、AIエージェントを“新しいチームメンバー”のように捉え、継続的に改善しながら共に働いているんです。
AIを導入するのは当たり前。その先を見据えて、自分の会社に、自分の業務に、どのように活かしていけるのかを考えてみてください。
▼こちらもチェックしてみてください!
【ホワイトペーパー配布】AI導入の“失敗”から学ぶ!成果につながる研修設計の鉄則とは?









